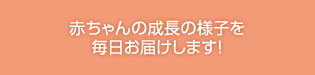関係者の声
東京・中野 新中野女性クリニック院長 海老原肇先生インタビュー①
社会起業プロジェクト「めるママ」では、お会いしたお産の現場の方々の生の声も積極的に伝えていきます。第1回目は、「絆メール」が始まったばかりの頃、テスト運用を引き受けてくださった新中野女性クリニックの海老原肇先生です。
![]()
高齢でのお産が増えてきた
 ―先生のクリニックの年間分娩数は約500。中野区ではもっとも多いそうですが、この地域はどういった妊婦さんが多いですか?
―先生のクリニックの年間分娩数は約500。中野区ではもっとも多いそうですが、この地域はどういった妊婦さんが多いですか?
他の産院さんに紹介させていただいている妊婦さんも含めると、年間約700~800人くらいになります。年齢層は一昔前と比べると高くなっていて、仕事を持っている方は6割くらいでしょうか。
昨今は、仕事を休むことができない、働きながら育てることはできないなどで、出産を迷われる方が目立ちます。家計や仕事の環境が整うまで待っていたら、高齢 出産になってしまったというお母さんも多い。高齢のお産は身体への負担がきついしリスクも高くなるためできるだけ避けたいのですが、背景には政治や福祉の 問題があるので、クリニックだけではどうにもできないのが現状です。
―バースプランは、広い範囲で希望に応えておられますね。
今は自然分娩か無痛分娩か、母乳にするか混合にするか、母子同室か別室かなど、実にさまざまお産のスタイルがありますが、それぞれに長所と短所があってな にがベストとはいえません。短所があるからと頭から否定するのではなく、長所もみて、最後はお母さん自身に産み方を選んでもらいたい。そうして納得しも らってたスタイルのお産をサポートするためにベストを尽くしたいと思っています。
だから私のクリニックでは、バースプランの選択肢をできる限り広く揃えて、お母さんに選んでいただくようにしています。選択肢を広くして、自分がどうしたいんだという意志のもとで産むことができる環境を提供できれば、それが一番いいですから。
―より安全なお産のための帝王切開が増える傾向にある中、先生のクリニックでは帝王切開がそれほど多くないように思いますが。
た しかに、より安全策をということで早め早めに帝王切開を選択することが増えているようですが、これは本当にいたしかたないことです。でも私は、多くのお産 はできるだけ早めに施策を講じれば自ずと帝王切開の割合は減ると考えていて、それがなんとかうまくいっているのかもしれません。とはいえ、必要と判断すればすぐに帝王切開に踏み切りますから、ケースバイケースです。自然分娩だけがベストというわけはありません。
![]()
「普通にうまれて当たり前」ではない
―先生は2001年に開業する前、横浜の聖マリアンナ医大横浜市西部病院の周産期センターで11年間務められていました。周産期センターはとてもきつい現場だと聞いていますが。
周産期センターは、普通の妊婦さんもいますが、地域の産院で母体に危険があると判断した場合や早産、また産後の新生児に危険がある場合の受け入れ施設で す。私がいた横浜市西部病院周産期センターは、年間分娩数が800件くらいで、そのうち年間130人くらいが地域の産院からの「母体搬送」(※)によるも のでした。
(※診療所(クリニック)や助産院では対応できない状態の妊婦を、周産期医療センターや設備が整った総合病院に移送すること)
搬送されてくる妊婦さんの中には、それこそ生きているのが不思議なくらいの方も少なくありませんでした。しかも、交通事故などではなく、普通の妊娠生活を送っていて、ある日突然そんな状況になることがあるんです。事実私は、悲しい例をかなり多くみてきました。
誤解を恐れずにいえば、妊娠は、生物学的にはちょっと「異常」な状態。赤ちゃんを産むその時期だけ、その準備のためにだけに女性の身体は劇的に変化します。 それは危ういバランスでかろうじて正常を保っているようなもので、お母さんへの負担はみなさんが思う以上に重くて、ちょっとしたきっかけでとんでもないこ とが起こりえます。
だからこそ、妊婦さんやその周りの人は、こうしたことをきちんと自覚した上で妊娠生活を送ってほしい と思っています。私は、妊婦さんに対して厳しい面があるかもしれませんが、それは周産期センターで、ちょっとしたきっかけでとんでもないことになった例を 多くみてきたからかもしれません。
日本は現在、母体死亡率、新生児死亡率ともに世界で一番低い国ですが、それが逆に、「普通にうまれて当たり前」だと誤解されることにつながっているようです。でも、そうではありません。「普通にうまれて当たり前」になったのは、先人のおかげ で医療技術や機器の進歩があったからだし、現場の医師ががんばっているから。妊娠・出産は本来、母体にとって負担が大きく危険なことなのは、歴史をひもと けば明らかです。あまりうるさくいうのも考えものですが、できればこうしたことをよく理解した上で、赤ちゃんを産んでほしいと思っています。一人の人間が 誕生するということは、実に貴重でかけがえのないことなんです。
(東京・中野 新中野女性クリニック院長 海老原肇先生インタビュー②に続く)
 新中野女性クリニック院長 海老原肇先生
新中野女性クリニック院長 海老原肇先生
(産婦人科学会専門医/母体保護法指定医)
聖マリアンナ医科大学にて医学博士号を取得
聖マリアンナ医大横浜市西部病院にて周産期センター医長および 産婦人科医長を兼務
2001年10月 新中野女性クリニック開院
新中野女性クリニックHP http://www.snwomen.net/
東京・中野 新中野女性クリニック院長 海老原肇先生インタビュー②
妊婦さんのためになるならと、試してみた
―ここからは「絆メール」ついてお聞きします。最初は、私たちがいきなりメールをお送りしてテスト運用をお願いしたわけですが、すぐに快諾してくださったのはなぜでしょうか。
前述の通りクリニックの年間分娩数は約500で、日々の外来数は100~150人くらい。外来数は誰にいっても驚かれます。つまり、これ以上妊婦さんが増えると、私の身体がいくつあっても足りないような状況です。だから、来院を促すための広告・宣伝のためのものなら、必要を感じていませんでした。
でも説明を聞くとそうではないようだったので、最初は「まあ会ってみるくらいなら」といった気軽な気持ちでした。試してみるかみないかは別として、話を聞けばアドバスくらいはできるかなと。その上で、それが妊婦さんのためになるものであれば、試してみてもいいかなと。
― 結果的にすぐにご快諾いただき、ありがとうございます。「絆メール」は妊婦さんに配信する準備として、産院の先生方に「基本原稿」の”カスタマイズ”、つまり産院の考えや方針に従って添削・修正をお願いするわけですが、このプロセスでとくに注意した点はあるでしょうか。
「基本原稿」は、めるママの皆さんが過去に同様のコンセプトの書籍を2冊作ったノウハウが反映されていると聞いていたので、お腹の赤ちゃんの発達プロセスなど、医学情報の面で問題はなさそうだと見ていました。実際に私自身が読んでみても、大きな問題はありませんでした。
気になるのは、クリニックの方針と異なった記述があるかどうか。それほど多くはありませんでしたが、明らかに異なっている部分はもちろん直しました。
あと私としては、「時期ごとに大事なことは、繰り返し伝える」ように手を入れました。例えば、妊娠初期のつわりへの対処法や、後期の陣痛時の対応の仕方など、よく理解してもらう必要があることは、繰返し原稿に入れるようにしました。重要なことは、一度読んだだけでは忘れてしまうかもしれないので、何度も繰り返し読んでもらうことでイメージを持ってもらうという感じです。このあたりは、編集を担当されたスタッフの皆さんがご存知の通りです。
先程も申し上げた通り、日々クリニックに来る妊婦さんが多いので、一人ひとりに妊婦さんに多くの時間を割けません。大事なことの説明も、どうしても急ぎ足になって伝わりにくい。その点を考えると、「クリニックから毎日メールでのアドバイスが届く」というのは、とても意味があることに感じています。
![]()
健診のフォローになっているかもしれない
―妊婦さんの反応はいかがでしょうか?
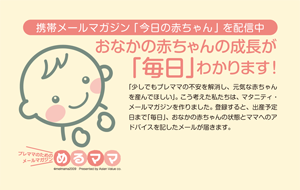
↑クリニックで使用中の登録カード。これが妊婦さんに手渡される。
「登録カード」(右画像)を渡すとき、「毎日お腹の赤ちゃんの情報がいきますよ」というと驚かれます。「毎日メールで届きます」というと、けっこうびっくりされる妊婦さんが多いですね。
でも「あなたの赤ちゃんではなくて、もちろん一般的な赤ちゃんの話ですよ」とはいいますが(笑)。それでも「そんなことをしてもらえるんだ」と、とても喜ばれています。
―健診時に、メールのことが話題になることがありますか?
1日あたり100~150人の外来があるので、こうした話をする時間がないのが正直なところです。妊婦さんのほうも、私が非常に忙しいことはわかるようですから、質問もしにくいでしょうし(笑)。だからこのメールマガジンが、案外フォローになっているかもしれませんね。
―どんな妊婦さんにも当てはまる内容のメールマガジンと、「産院オリジナルメールマガジン」では、どのような違いを感じておられますか?
産院として気をつけてもらいたい内容を入れることができる点でしょうか。こうした部分は、どこの産院もだいたい似たような内容になるかもしれませんが、同じことでも伝え方次第で、妊婦さんの受け取り方は変わると思います。微妙なニュアンスの違いを表現できたり、こちらがとくに知らせたいことを伝えることができるのが、「オリジナル」のいい部分かもしれません。
―最後に、妊婦さんへのメッセージをお願いします。
お産は本当に大変なものですが、赤ちゃんと逢えたらその喜びは本当に大きいし、子育てには苦労もありますが、同時に人生の大きな楽しみと喜びがあると思います。子どもを産むことは、女性にしかできない大きな仕事です。中には妊娠やお産を女性に課せられた義務のように感じる方もいらっしゃいますが、女性にしか許されていない権利でもあるのです。男性はどんなに産みたくても産めない。だからもし、女性として赤ちゃんを産む幸運に恵まれたのなら、それを本当に大事にしてもらいたいと思っています。
―ありがとうございました。
![]()
[編集後記]
当時はまだその名前さえも決まっていなかった「絆メール」のテスト運用を、まずはメールで先生にお願いし、その後電話をしたことを昨日のことのように覚えています。先生からすれば、よくある営業電話のひとつだったかもしれないし、よくわからない人間からの怪しい申し出だったかもしれないのに、頭から否定せずお会いしてくれたこと、さらに主旨に賛同してテスト運用をその場で快く引き受けてくれたことに、本当に感謝の気持ちで一杯です。
その後何度か先生のクリニックに通ううちに、先生が料理好きで、ときに自ら腕をふるって入院中の妊婦さんに振る舞われること知りました。そこで取材後に、「人気のメニューは?」とお聞きしたところ、「キッシュと中華粥でしょうか」との答え。本格的すぎて恐れ入りました。
 新中野女性クリニック院長 海老原肇先生
新中野女性クリニック院長 海老原肇先生
(産婦人科学会専門医/母体保護法指定医)
聖マリアンナ医科大学にて医学博士号を取得
聖マリアンナ医大横浜市西部病院にて周産期センター医長および 産婦人科医長を兼務
2001年10月 新中野女性クリニック開院
新中野女性クリニックHP http://www.snwomen.net/